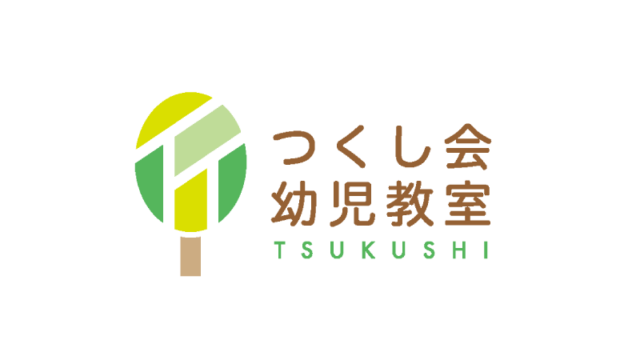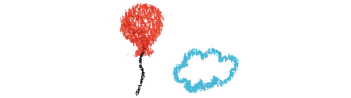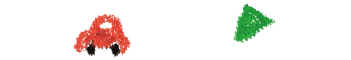今も昔も子どもの習い事の定番である「水泳」。お子さんに習わせたことがある、もしくはこれから習わせてみたいと思っている方も多いのではないでしょうか。自身もジュニアオリンピック大会に出場するなど選手として活躍した後、30歳の若さで慶應義塾体育会水泳部の監督に就任した川原 篤人さん。監督として指導する際に気をつけていることや、延べ100名以上の選手を指導する中で見えて来た、伸びる選手と伸びない選手の違いなどについて伺いました。

1985年生まれ。慶應義塾幼稚舎、慶應義塾普通部、慶應義塾高等学校を経て2008年慶應義塾大学環境情報学部卒業。会社員として金融機関に勤務する傍ら、2016年にボランティアとして慶應義塾体育会水泳部監督に就任。2021年のインカレで23年振りとなるシード権を獲得した他、オリンピック日本代表、インカレ優勝選手等多数輩出。日本スポーツ協会公認水泳コーチ4保有。自身は10カ月から水泳を始め、全国中学校水泳競技大会入賞、ジュニアオリンピック大会出場。大学在学中の2004年から高校生および大学生を対象としてコーチングを開始し、以降一貫して慶應義塾体育会水泳部の指導に当たっている。
30歳で監督就任 順風満帆ではなかった1年目
石井氏
―川原さんは30歳で慶應義塾体育会水泳部の監督に就任されました。異例の若さだと思いますが、監督就任のいきさつから聞かせてください。
川原氏:もともと私自身が慶應義塾体育会水泳部の出身で、卒業後もずっと社会人コーチとして部に携わっていました。そんな中、2016年に前監督が退任し、私が引き継ぐことになりました。私はコーチ時代から、リクルーティングにかなり力を入れていたんです。高校3年間と大学4年間の「7年計画」で選手を育成したいと考えていたので、一貫校の一つである慶應義塾高等学校の入試を受けてもらうために、全国を渡り歩いて中学生を勧誘していました。そうやって私が声を掛けて高校から入ってきた選手たちが、ちょうど大学に上がるタイミングでもあったので、「川原にやらせてみよう」という話になったのだと思います。
石井氏
―一貫校の強みを生かして、若い世代から育成したほうが合理的だと考えたのでしょうか?
川原氏:おっしゃる通りです。もともと、大学の4年間だけでは、育てるにしても限界があると感じていました。また、当時は大学の勧誘がうまくいっていなかったという実態もあって。すでに活躍している選手に声を掛けても、他の強豪校に行かれてしまうことが多かったんです。それならば高校生のうちから7年間かけて育てることで、はじめは泳げなかった子でも全国大会の決勝に残れるぐらいのレベルを目指したいと考えたのです。ちなみに、一貫校との関わりという意味では、大学生が中学や高校の部活動を訪問して一緒に練習したり、一貫校を含めた記録会を年に2回開催するなどの機会を増やすようにしているところです。
石井氏
―インカレで23年ぶりのシード権を獲得するなど数々の功績を残されていますが、就任当初から順風満帆だったのでしょうか?
川原氏:いえ、はじめの1年ぐらいは思い通りにいかないことも多かったですね。当時は、部を強くしたいと思うあまり、力が入りすぎてしまっていたと思います。例えば、就任してすぐに、まずは練習量を増やそうと考えたんです。でも、学生に大反対されて。「そんなやり方なら僕らはやりません」とまで言われてしまいました。学生たちも、ただ感情的に「嫌だ」と言ってきたわけではないんですよ。自分たちには授業と練習があって、そのほかに休息をしっかりとることもアスリートとして必要なんだと。そこまで考えて、「自分たちはこのバランスでやっていきたい」と言われて。あぁこれは敵わないなと思った瞬間がありました。どちらが正しいか、正解は分かりません。でも、本人たちがそう思っている以上は、仮に強制的に練習量を増やしてもあまり機能しないだろうと。こういった経験を通じて、自分でも徐々に肩の力が抜けていったように思います。

慶應義塾体育会水泳部のメンバーと
カギは「自分で考える」「聞く耳を持つ」
石井氏
―これまでに延べ100名以上の選手を見てきて、伸びる選手と伸びない選手の違いはどんなところにあると感じますか?
川原氏:明確に言えるのは、「考えているかどうか」ですね。なぜ自分は今調子がいいのか、悪いのか。もしくは、なぜ自分のタイムが速くなったのか。そういったことを自分なりに考えて分析し、言語化して人に説明できるかどうかということです。それができる人はやっぱり強いですし、ちょっと崩れたときでも、「じゃあここを修正してみよう」という発想が生まれてくる。言語化することで自分の頭の中が整理され、結果的に今自分が何をすべきかを理解できるようになるのだと思います。
石井氏
―「自分で考える」ということは、スポーツを通じて学んでいけば身につけられるものなのでしょうか? それとも幼い頃の家庭環境などの影響が大きいと思いますか?
川原氏:どちらか一方ということではなく、両方とも大事だと思います。私自身の幼少期を振り返ると、両親から何か言われたという記憶はあまりなく、自由にやらせてもらっていました。水泳のレッスンに行くときに「ちゃんとやりなさいよ」とか「先生の話をよく聞きなさいよ」などと言われたこともなかったですし。その代わり、責任は自分で取りなさいという感じでしたね。そういう環境の中で育ったことが、「自分で考える」という姿勢にもつながっているのかなと思います。
石井氏
―逆に伸び悩んでしまう人は、自分できちんと考えが整理できていないということでしょうか?
川原氏:そうですね。自分の中でいろいろと考えてはいても、最終的に整理がつかないまま、答えが見いだせずに終わってしまう選手もいます。あとは、どちらかというと頑固で、偏った考え方のまま、それを曲げられないタイプの選手も多いですね。「聞く耳を持つ」ということはとても大事だと思います。そして、そのためには「素直さ」が絶対に必要です。これまで数多くの選手を見て来た経験から、やはりコーチや監督の話をよく聞く選手はきちんと伸びていくなという感覚はあります。逆にそうではないケースもたくさん見てきたので、素直に耳を傾けることは本当に重要だと感じています。
部活動として一番大事なのは結果ではない
石井氏
―監督と仕事を両立するのは大変だと思うのですが、なぜその道を選んだのですか?
川原氏:一つには、自分自身も水泳部でいろいろな人にお世話になったので、何か部のために役に立てることがあるならやりたいなという思いがありました。あと、会社で学んだことは部に還元できて、部で学んだことは会社に還元できている気がするんですよね。それは、なかなか他の人にはできない貴重な経験だと感じています。20代のころは今より会社の仕事も忙しく、金曜の夜中まで働いてそのまま土曜の朝練に参加する、ということもありました。でも、かなり負担がかかっているはずなのに、やっぱり楽しいんですよね。むしろ、もし当時水泳がなくて仕事だけしていたら、病んでしまっていたかもしれません(笑)。両方があることで、うまくバランスが取れているのだと思います。
石井氏
―体育会の監督という立場から見て、部活動としての成功とは何だと思いますか?
川原氏:私が強く思っているのは、「卒業した後に良かったと思えるかどうか」です。極端に言えば、大事なのは結果ではないんです。例えどんなに結果が良くても、卒業した後に同期で集まるとか、そういうことができなければ失敗だと思います。逆に結果が全然出なくても、卒業した後に部に帰ってきてくれたり、仲間同士の付き合いが続いたりしていくようであれば、大学の部活動としては成功だと。もちろん、水泳で勝負しようという気持ちで頑張っている学生たちに対して、「結果なんて出なくてもいいんだよ」と言うつもりはありません。ただ、体育会はプロではないし、お金をもらっているわけでもない。だからこそ、最終的に「やって良かった」と思えるかどうかが、本人にとっても部にとっても、結果以上に重要なのではないかと考えています。
「失敗させる勇気」を持って接することが大事
石井氏
―昨今、水泳は習い事としても非常に人気が高いですよね。水に親しむためには、やはりできるだけ小さい頃から習い始めたほうが良いのでしょうか?
川原氏:「恐怖心をなくす」という意味では、小さいうちに始めたほうがより良いのかもしれません。ただ、競技として見ると、中学生・高校生から始めても全く問題ないと思います。むしろ海外では、中学生ぐらいまでは水泳以外にもいろいろな競技をやってみて、高校生ぐらいから水泳一本に絞っていく、というタイプの選手のほうが圧倒的に多いです。私自身も、小さい頃はさまざまな競技を通じて、体の動きの多様性や柔軟性を鍛えていく方が良いのではないかという気がしています。
石井氏
―お子さんにスポーツをさせたいと考えている親御さんに向けて、アドバイスなどがあればぜひお願いします。
川原氏:ぜひ、お子さん自身に失敗をさせてあげてください。例えば水泳だったら、周りの子どもと比べて早く進級させたいとか、早く上の段階にいかせたいとか、そういうことを考えるのが親心ですよね。ただ、そうやって急いで上の段階に行っても、実はあまりいいことはないんです。それよりも、たくさん失敗したほうがいい。失敗を通じて本人が学べることの方が大きいので、むしろその後に伸びる要因になることが多い気がします。親や指導者から見て、「ここで右に行ったらうまくいかないだろうな」とわかっていたとしても、それは伝えずに、まずは本人が右だと思ったら右に行かせてみる。そういう度胸というか、勇気を持って接することが大事なのかなと思います。
(聞き手/株式会社LOCOK代表取締役、金沢工業大学虎ノ門大学院准教授 石井大貴)