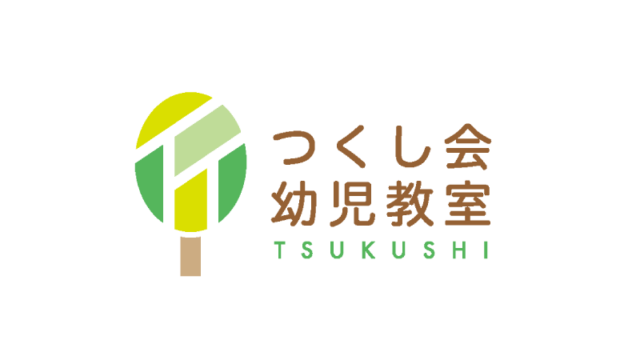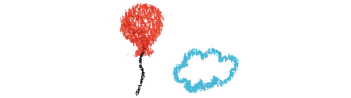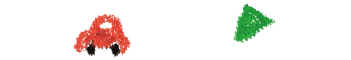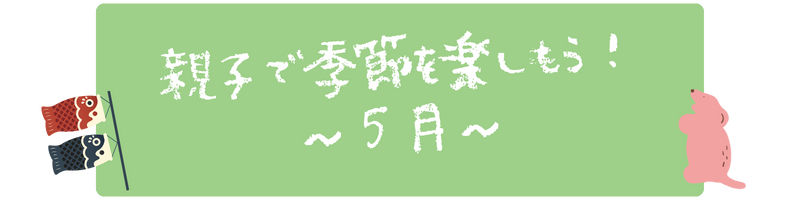
5月は、春から初夏に移り変わる時期。暑すぎず寒すぎず、湿度もそれほど高くないため、さわやかで過ごしやすい季節です。入園・入学などによる新生活に少しずつ慣れてくるタイミングともいえるでしょう。一方で、大人・子どもに関わらず、新しい環境の変化についていけずに「五月病」のような状態になる人もいるかもしれません。そんなときは一歩外に出て、新緑の香りのする風を思い切り吸い込み、深呼吸してみるのもよいかもしれませんね。
5月の自然
皐月(さつき)
 5月の和名。田植えの月であることから「早苗月(さなへつき)」と言っていたのを略したという説や、稲を植えることを「さ」と呼んでいたことが由来だとする説などがあります。
5月の和名。田植えの月であることから「早苗月(さなへつき)」と言っていたのを略したという説や、稲を植えることを「さ」と呼んでいたことが由来だとする説などがあります。
アスパラガス

若い芽を食用とするユリ科の野菜。欧州では紀元前から栽培され、日本には江戸時代に伝わりました。アスパラガスから発見された成分で疲労回復効果のあるアスパラギン酸が豊富。
夏みかん
 日本原産の果物で、初夏に楽しめる柑橘類。収穫時期は4月中旬から5月下旬で、夏ごろまで出回ります。酸味が強く、甘酸っぱい風味の中にほのかな苦味を感じる味わいが特徴。
日本原産の果物で、初夏に楽しめる柑橘類。収穫時期は4月中旬から5月下旬で、夏ごろまで出回ります。酸味が強く、甘酸っぱい風味の中にほのかな苦味を感じる味わいが特徴。
薫風(くんぷう)
 薫風とは、初夏に若葉の香りを漂わせて吹く快い風のこと。初夏の時候の言葉で、俳句では夏の季語でもあります。初夏のさわやかな季節を象徴する、代表的な言葉の一つです。
薫風とは、初夏に若葉の香りを漂わせて吹く快い風のこと。初夏の時候の言葉で、俳句では夏の季語でもあります。初夏のさわやかな季節を象徴する、代表的な言葉の一つです。
5月の行事
★端午の節句

どんな行事なの?
5月5日の「端午の節句」には、男の子が強く元気に育つことを願い、鯉のぼりや五月人形を飾ってちまきや柏餅を供えます。また、菖蒲をお風呂に入れたり屋根に乗せたりもします。
どうやって始まったの?
古代中国の影響を受けて、厄除けの儀式として行ったのが始まり。江戸時代の武家社会による風習から、鎧や兜が飾られました。鎧兜は武将の象徴であり、身を守る大切な道具であったことから、子どもを災害や事故から守るという願いが込められるようになりました。
まめ知識
鯉は、流れが速い川でも元気に泳ぎ、滝をものぼってしまう強い魚。鯉のぼりには、そんな鯉のように子どもたちが元気に育つことを願う意味が込められています。また、五色の吹流しは、子どもの無事な成長を願い、悪いものを追い払う意味が込められているのだそうです。
5月の記念日
東京港開港記念日(5月20日)
 1941年のこの日、芝浦埠頭・竹芝埠頭が完成し、東京港が国際貿易港として開港の指定を受けました。これを記念して、東京都が記念日に制定。毎年、記念日前後には「東京みなと祭」が開催され、首都圏の暮らしを支えてきた東京港の歴史と役割などを伝えています。
1941年のこの日、芝浦埠頭・竹芝埠頭が完成し、東京港が国際貿易港として開港の指定を受けました。これを記念して、東京都が記念日に制定。毎年、記念日前後には「東京みなと祭」が開催され、首都圏の暮らしを支えてきた東京港の歴史と役割などを伝えています。
こんにゃくの日(5月29日)
 種芋の植えつけが5月に行われることと「こ(5)んに(2)ゃく(9)」の語呂合せから、日本こんにゃく協会と全国こんにゃく協同組合連合会が1989年に制定。本格的な夏を迎える前に、こんにゃくの効用を再確認し健康に過ごして欲しいという願いも込められています。
種芋の植えつけが5月に行われることと「こ(5)んに(2)ゃく(9)」の語呂合せから、日本こんにゃく協会と全国こんにゃく協同組合連合会が1989年に制定。本格的な夏を迎える前に、こんにゃくの効用を再確認し健康に過ごして欲しいという願いも込められています。
5月の誕生花
カーネーション
 ナデシコ科の多年草。母の日の贈り物としても有名です。赤色のイメージが強いカーネーションですが、ピンク、オレンジ、黄色、青色など豊富な色があります。丈夫で育てやすいことから、鉢植えギフトも人気だとか。花言葉は、「無垢で深い愛」「感謝」「永遠の幸福」。
ナデシコ科の多年草。母の日の贈り物としても有名です。赤色のイメージが強いカーネーションですが、ピンク、オレンジ、黄色、青色など豊富な色があります。丈夫で育てやすいことから、鉢植えギフトも人気だとか。花言葉は、「無垢で深い愛」「感謝」「永遠の幸福」。