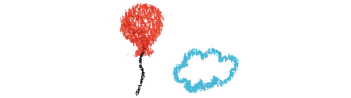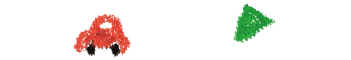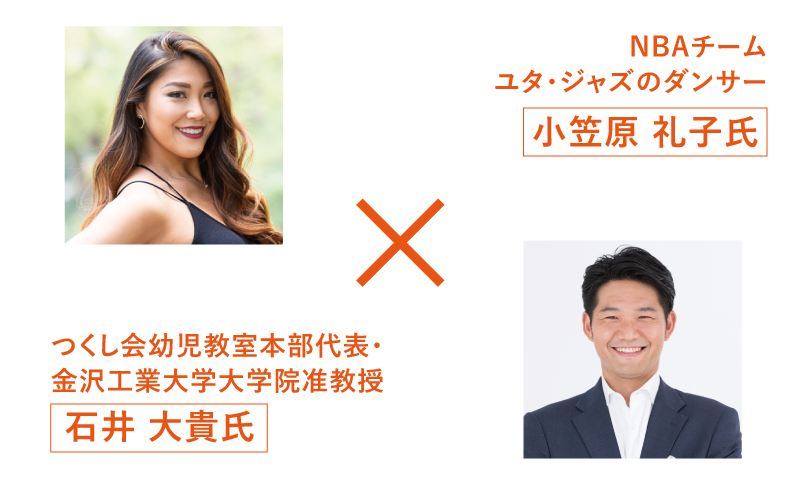
アメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクシティに本拠を置く全米プロバスケットボール協会(NBA)のチーム、ユタ・ジャズのダンサーとして活躍されている小笠原礼子氏。高校時代にチアリーディングに出会い、20代後半でチアダンスに転向。本場アメリカで踊りたいと30歳を過ぎてからNBAに挑戦し、見事夢を叶えました。多くの人に勇気と笑顔を届ける小笠原氏に、夢に近づく秘訣などをうかがいました。
「家族を笑顔に」が今の活動の原点

石井氏
―小笠原さんはコロナ禍にありながら、自分の夢のために渡米してオーディションを受けて合格。また次のチームに挑戦されるなど、一般的にはなかなかできないことに挑んでいます。NBAダンサーのオーディションではとても堂々とされていました。昔から物おじしなかったのでしょうか。
小笠原氏:いえいえ、私はポジティブに見られがちなのですが、実はそうではなくて・・・だからこそちゃんと準備するというか、ネガティブなことを考え尽くして最悪のパターンを想像するんです。オーディションでもダメだったときのことをすべて考えた上で、「それは嫌だから頑張る」というモチベーションで挑んでいます。
石井氏
―チアダンスを本格的に習い始めたのが20代後半と比較的遅めです。心配するタイプでありながらも、なぜ挑もうとしたのでしょうか?
小笠原氏:心配性な反面、好奇心はすごくあって、何も知らない状態というのは私にとっては飛び込みやすいんです。逆に自分の位置がわかっていると飛び込みにくい。身の程知らずだから挑戦できたのかもしれませんね。基本的に自分に対して自信がないので、オーディションの中で「落ちたらどうしよう」とは考えます。自信はないのですが、「オーディションに合格したい」「コートに立ちたい」「やりたい」という気持が強くあります。でも小さい頃ダンスはやっていませんでしたし、まさか自分がダンサーになるなんて、家族も思っていなかったと思います。
石井氏
―どんなお子さんだったのですか?
小笠原氏:三姉妹の末っ子で甘えん坊。目立ちたがり屋でしたが、運動や勉強は姉二人に劣っているという意識がすごくありました。3歳からしていた水泳も、姉たちは育成選手なのに私は違う。ドジでのろまというポジションを自分で自分に与えていました。それを跳ね返す意味でおちゃらけたりして。家族のムードメーカーでしたね。
石井氏
―みんなのムードメーカーになるというのは、まさにチアの世界と同じですね。周囲の人を笑顔にする喜びに気づいたのは、やはり家族の中での立ち位置が影響しているのでしょうか?
小笠原氏:多分そうだと思います。チアが自分にフィットしたのは、私自身のパーソナリティ、小さい頃から家族を笑顔にする、というところから始まっていると感じます。
チアのユニフォームに一目惚れ

石井氏
-地元青森県の公立高校に進学し、そこでチアリーディングに出会ったそうですが、きっかけは何だったのでしょうか?
小笠原氏:中三のとき、高校選びのため見た学校のパンフレットに、たまたま同じ藤崎町出身で同じピアノ教室だった先輩がポンポンを持ってユニフォームを着ている写真が掲載されていたんです。それを見て「この学校に行く!」と決めました。ユニフォームがすごくかわいかったんです。無事合格して入部すると、本格的なチームではありませんでしたが、見よう見まねで頑張りました。
石井氏
-そこからチアダンスに至るまでの道のりについて教えてください。
小笠原氏:大学でもチアリーディングを続け、卒業後は本格的に競技チアリーディングを学ぶため、あまり考えずに上京してしまいました。とりあえずバイトでも何でもいいから上京してから決めればいいや、と。
石井氏
-結構大胆ですね。目指すものが見つかったらそれを確実に成し遂げたいから石橋を叩いて渡る。「嗅覚」と「確実に成し遂げてく力」というのは両方備わっていないとなかなかできません。そのバランスがすごい。
小笠原氏:飛び込む力はすごくあるかもしれません。飛び込んでから成し遂げるまでは結構時間がかかりますが。20代はコンプレックスの塊で、人のことをうらやましいとばかり思っていました。地方出身なのにも引け目を感じていました。30歳を超えて自分を客観視できるようになりましたが。
石井氏
―上京して就職されていますよね。
小笠原氏:はい。スポーツ支援に積極的な企業に就職しましたが、その会社が持っているチアチームではなく、正社員として皆と同じようにフルタイムで働き、オフのときに社会人クラブチーム・デビルズで活動していました。チアリーダーとしての活動を続けるためには、生活基盤をしっかり確立させることが大事ですから。10年近く勤めましたが、すべてが今に繋がっていると感じます。会社員として働いて社会性を身につけた上で現在のキャリアを築いたのは、自分の強みだと思っています。今いろいろなお仕事をいただけるのもそのお陰だと感謝しています。
石井氏
―チアダンスに移ったのはチアリーディングで日本一になったことが契機だったのでしょう?
小笠原氏:はい。結果を残せたこと、また強い絆で結ばれた仲間と納得できる演技をして引退したいと思っていて、それが達成でき、やり切った感がありました。チアリーディングは人を肩に乗せたりとアクロバティックな演技が中心で、体にかなり負担があります。なので、40歳50歳までやろうとは思えなかったのも転向理由の1つです。チアダンスだったら何歳でもできると思いますし、実際、長く続けられる方もいます。続けていると、からだの動きにも品格が備わると感じるので、日々積み重ねることはとても大切だと思います。
「何にでもなれるよ」という祖父の言葉が力に

石井氏
―小笠原さんはチアダンサーに転身してからも、様々なチャレンジを続けています。その原動力につながるような、幼少期に親から経験させてもらってよかった、あるいは言われてよかったと感じることはありますか。
小笠原氏:祖父がよく私に言ってくれたのが、「礼子ちゃんは何にでもなれるよ」ということです。姉たちに同じことを言っていたかはわかりませんが、二人だけのときに言ってくれていました。私が「姉たちより自分はできない」とコンプレックスを持っていることに、祖父は気付いていたのだと思います。
石井氏
―すてきなお話ですね。ところで教育面でいえば、これからの日本は自主性を持って人を巻き込む力がある人をもっと育てていかなくてはと思うのですが、小笠原さんはどう考えますか?
小笠原氏:私もそう思います。アメリカではレッスンでいきなりフリースタイルが与えられます。日本人は決まった振り付けを完璧にこなすことはできても、これはすごくハードルが高い。でもアメリカ人はすぐ自分の表現ができます。私は今の日本の教育現場をよく知りませんが、ダンスでいえば、自分の発想通りに体を動かして表現する場面は、日本は欧米より少ないのではないかと思います。
石井氏
―体を動かすというのは、単純に運動をするということだけではなく、脳からの指示によって動いているわけです。つまり幼少期に大人からどんな質問をされるか、どんなインプットを受けるかによって、その人の動きや言葉、表現の仕方は変わると思います。だからこそ自主的に考えられる大人が、子どもを後押ししていかねばならないと思います。
小笠原氏:その通りだと思います。やはり幼少期は世界が狭く、そばにいる大人がすべてになりますから、その大人が自主性を持っていたり、子どもに求めるだけではなくて大人自身が夢を追っている、チャレンジしている姿を見せたりするのは大切なことですね。
石井氏
―今後も共働きが増え、教育がどんどんアウトソースされ、先生たちの役割が今まで以上に重要になっていくでしょう。そこに小笠原さんみたいな人がいるとすごくいいと思います。
小笠原氏:ありがとうございます。ただ先生方が全部対応する必要はなくて、先生方はそのプロで、私は私がプロとしてやっている部分を提示していきたいですね。いろんなものを引っ張ってきて、お子さんが様々な世界を知ることができる環境があるといいと思います。私も幼い頃にいろんな習いごとをしました。それで一番になれなくても、今大人になって生かされていることもたくさんあるので、やはりいろんなことをやれる環境というのは大切だと思います。
どんなチャレンジ、どんな結果であろうと家族が味方に

石井氏
―次世代にはどんなことを伝えていきたいですか?
小笠原氏:一番伝えたいのは「チャレンジすること」です。飛び込むことを伝えたいですし、伝えるために今自分がこの活動をしていると思っています。私自身のことを踏まえて言うと、今はありがたいことに結果が出てきていますが、最初はそうではありませんでした。ですから、小さい頃や10代、20代のときに結果は出なくても、巡り巡って現在の結果に繋がる、必ず返ってくると思うのでいろんなことに挑戦してほしい。「今は結果は大事ではなくて、チャレンジすること自体が大事だ」と思うといいかもしれません。あきらめない気持ちも大切ですね。
石井氏
―ご自身はこれから先、どんなビジョンを描いていますか?
小笠原氏:具体的なビジョンというのはないのですが、決めているのは「人のために何かをやっていきたい」ということです。ダンスや海外生活のノウハウなど、特定のテーマにフォーカスしたことではなく、私の経験から得たことを広く伝えたいですね。学校単位で広められればいいなと考えています。
石井氏
―最後に子育て世代にメッセージをお願いします。
小笠原氏:私自身は子育て経験はありませんが、子どもだった経験はあるのでそれを踏まえていうと、やはりいろんなことにチャレンジさせてもらえる環境は、当たり前ではありませんが、大事だと思いますし、そのチャレンジするときに親が一番の味方でいてほしいと思います。つらいときには電話で励まされるなど、この歳になっても、やはり親が一番の味方になってくれています。でもそれは大人になってからできる絆ではなくて、小さい頃からの「どんなときも親や家族が支えてくれた」という思いが蓄積されて強固な信頼関係になるのだと思います。ですから、どんなチャレンジでどんな結果であろうと、家族には子どもの一番の味方でいてほしいと思います。
(聞き手/LOCON株式会社代表取締役、金沢工業大学虎ノ門大学院准教授 石井大貴)