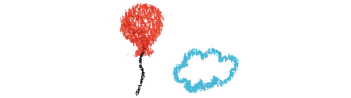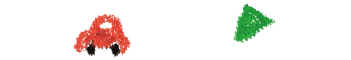「現代美術」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか? 「自由で面白い」「ちょっと難しくて敷居が高そう」など、人それぞれのイメージがあるかもしれませんね。今回お話を伺ったのは、植物や自然と人間の共存をテーマに、絵画を中心とした作品で国内外から高い評価を受けている現代美術作家の平子 雄一氏です。日本のみならず、欧米やアジアの美術館やギャラリーで作品が展示され、その独自の世界観は多くの人々を惹きつけています。そんな平子さんに、子どものころ見ていた景色や育った環境が自身の創作活動に与えた影響、次世代を生きる子どもたちに伝えたい思いなどを語っていただきました。

現代美術作家 平子 雄一さん
1982年 岡山県生まれ、東京を拠点に活動。2006年にイギリスのウィンブルドン・カレッジ・オブ・アートの絵画専攻を卒業する。植物や自然と人間の共存について、また、その関係性の中で浮上する曖昧さや疑問をテーマに制作を行う。ペインティングを中心に、ドローイングや彫刻、インスタレーション、サウンドパフォーマンスなど、表現手法は多岐にわたる。ロンドン、ロッテルダム、上海、ソウルなど、国外でも精力的に作品を発表している。
自然に囲まれ一人遊びに熱中した幼少期
石井氏
―岡山県のご出身とのことですが、幼少期はどんなお子さんでしたか?
平子氏:田園と畑に囲まれて、ちょっと遠くを見れば山があるような、そんな景色の中で育ちました。友達と遊ぶよりも、一人で草むらや林に行って、昆虫採集や植物採集をするのが好きでした。虫や植物を見ながら、「これは何だろう」と物の成り立ちを考えるのが楽しかったんです。だからといって、俗にいう大人しい子どもではなかったし、友達がいないわけでもなかったんですよ。なので、周りはみんな不思議がっていたと思います。普段は仲良く接しているのに、遊びの誘いになると必ず断るので(笑)。
石井氏
―そうやって幼少期に一人遊びをしていた経験は、現在のアーティストとしての活動に反映されていると感じますか?
平子氏:明らかに反映されていると思います。現代美術の作品を作る上で、まずメインになってくるのは「思考」なんです。「技術」を習得するだけでは、結局いい作品は作れない。昔の工芸であれば、技術の積み重ねがあればいいものが作れたかもしれません。でも、現代美術の場合は、独自性が主に求められます。ですから、常に自問自答を繰り返す必要があるのです。実際、私もイギリスに留学した大学時代は、この「思考」の部分ばかりを鍛錬させられました。そういう点で、幼少期に一人遊びをしながら「これは何だろう」と考え続けていた経験が、今につながっていると思います。
石井氏
―ちなみに、子どもの頃は勉強や運動は好きでしたか?
平子氏:勉強はある程度できましたけど、のめり込むほど好きではなかったです。運動は、剣道を5年ぐらい習っていました。あとは、中学・高校と自転車で通学していたので、それでかなり足腰が鍛えられたと思います。学校が遠くて、中学校はゆっくり漕ぐと30分、高校は一時間以上かかっていました。そのせいか、足がすごく早くなって、当時50メートル走は6秒台を切っていたんですよ。運動部の友達には、「お前、何なんだよ」と嫌な顔をされていました(笑)。
留学先で感じたギャップが制作の原点に
石井氏
―初めて絵を描くことが楽しいと思ったきっかけは何だったのでしょうか?
平子氏:小学生のころ、鳥山 明先生の漫画「ドラゴンボール」にはまったことがきっかけです。「ドラゴンボール」のストーリーというより、線の美しさにすっかりはまってしまって。コミックのページを拡大コピーして、トレーシングペーパーを重ね、上からずっと線をなぞっていました。ただ、きれいなものを写し取りたかったんです。漫画の内容は全然頭の中に入って来なくて、ひたすら無心で線をなぞり続けていました。
石井氏
―植物や自然と人間の共存というテーマで作品を作るようになったのはなぜですか?
平子氏:私にとって自然は、子どもの頃から身の回りに当たり前のように存在しているものでした。ところが、20歳で留学したロンドンでは、公園や街路樹ぐらいしか自然に接することができる場所がなくて。私からすると、公園も街路樹も「人が作ったもの」としか思えなかったのですが、ロンドンに住む人たちはそれが「自然」だと言う。そのギャップに驚いたんです。そこから、自然とはそもそも何なのだろうと考え始めました。自然の定義は人によって違うし、状況や時代によっても変わります。この不確定な部分を作品に落とし込むことで、初めてアートとしての意義が生まれるのではないか。そう考えてこのテーマに辿り着きました。
石井氏
―平子さんの作品には、木と人が融合した人物がたびたび登場します。あの印象的なモチーフはどうやって誕生したのでしょうか?
平子氏:一般的には、自然と言えば「美しい」「癒される」「守るべきもの」といったポジティブなイメージでとらえられることが多いですよね。でも、これらのイメージは、全て後天的に得られるものだと思うのです。恐らく人間以外の動物は、自然を見ても「癒されるなぁ」とは感じないだろうし、人間も「自然はいいものだ」という環境の中で育たなければ、そう感じるようにはならないはずです。でも、特に先進国の人たちは、ほとんどの場合「自然はいいものだ」という共通認識を持っている。このほとんどの人が共通して持っているものを、どう具現化しようかと考えた結果、頭部が植物でできたあの登場人物が生まれました。


2025年秋に開催された「平子雄一展 ORIGIN」にて
自身の内面を問われ続けた3年間
石井氏
―ロンドンへの留学は、ご自身で決められたのですか?
平子氏:はい。日本の美大や芸大は、入学試験でも基本的にデッサンが重視されます。デッサンができなければ、そもそも合格できない。その仕組みに、どうしても納得いかなくて。それから、あるときイギリス人作家の作品集を見る機会があったんです。それがとにかくかっこよかった。しかも、明らかにデッサンの訓練をしていない人たちが、とても魅力的な作品を作っていて。実際にロンドンへ行ってみると、先生たちも「デッサンの技術は必要ないから」という感じでした。
石井氏
―日本とイギリスではそもそもメソッドが違うということですか?
平子氏:全く違いますね。日本では、まず描き方や技術を身につけてから、自分の表現を追求します。一方、イギリスをはじめとする欧米では、「自分の中に何があるのか」を探るところから始まります。授業ではまず、「とりあえず何か描いてみて」と大ざっぱに言われます。何か描くと、「なぜこれを描いたのか」「そこにはどんな意味があるのか」と、徹底的に問いかけられる。まるでカウンセリングのようでした。さらに、「あなたは何に影響を受けて、こういう表現に至ったのか」と問われ、それを踏まえてもう一度描き直す。すると今度は、「この配置や色にはどんな意味があるのか」と、また問い直される。その繰り返しを、3年間ひたすら続けるんです。だから、技術的には誰も上達しないんですよ(笑)。
石井氏
―徹底的に思考の部分を鍛錬されるのですね。
平子氏:そうです。今振り返ると、「あなたが生み出すものが、この世界にとって本当に必要なのかを考えなさい」と言われていたのだと思います。芸術の世界は、一見すると優劣がないように見えますが、実はすごく優劣があるんです。正確には、優劣というより、社会にとって必要か、不必要かという基準ですね。そのことを突き付けられて、私の同級生の90%以上は、卒業後すぐに制作活動をやめてしまいました。ほとんどの人は「そこまでして作る必要はないな」と、自分自身で気付かされるからです。
深く考える起点としてアートを使ってほしい
石井氏
―平子さんが以前、「自分の作品が後世に残る可能性は0.001%かもしれない。でも、できればそうなりたい。そのために必要なのは、最後は“気合い”だ」とおっしゃっていたのがとても印象に残っています。どのような考えでそう発言されたのでしょうか?
平子氏:ふと、今自分がやっていることは、何の意味もないかもしれないと感じることがあるんです。もしかしたら誰にも評価されないかもしれない。それでも、がむしゃらに進んでいかなければいけない。そのためには立ち止まって考えている暇はないというか、もう気合でやり続けるしかないと。そう思うようになったきっかけは、父の死でした。人が達成できることには限界があるのだと気付かされたのです。元気に制作できるのが70歳くらいまでだとして、その間に成し遂げなければならないことがあると考えたら、もう悠長に構えていられないなと。そこから探究の深度が明らかに深まり、制作のスピードも上がっていきました。
石井氏
―これからどんな作品を作っていきたいですか?
平子氏:どんなにいいものを作っても、次はもっといいものが作れるはずだと思ってしまうので、「自分自身が満足することはない」というのが前提としてあります。その上で、今の自分にできる最大限のものを作り続けていきたいです。あと、一つ意識しているのは、私の作品を見てくれた人が「すごくいい」と思うだけで終わらせたくない、ということです。「いい」という感想が生まれた時点で、その人の思考は一度止まってしまっている。そうではなくて、「ちょっとよくわからないけれど、何だかいい気がする」と感じるような、少し先を行く表現を目指したい。そして時間をかけて、「あぁ、だからこの作品はいいんだ」と徐々に腑に落ちていく。そんな作品を作っていきたいですね。

アトリエにて制作活動中の平子氏
石井氏
―これからを生きていく子どもたちに対して、メッセージをお願いいたします。
平子氏:アートの世界は、クリエイティブで華やかなイメージがあるかもしれませんが、実際には、どれだけ努力してもどうにもならないという現実が常につきまといます。ですから、一概に「ぜひ目指してください」とは言えません。一方で、思考の幅は、できるだけ広げたほうがいいと思っています。それはどんな分野にも応用できる力だからです。アートの役割は、まさにそこにあると思います。「なぜこれが存在しているのだろう」と考え、その問いによって生まれた余白を少しずつ埋めていく。そうやって深く思考するための起点としてアートを使ってもらえれば、見る側も作る側もより楽しくなると思います。
(聞き手/株式会社LOCOK代表取締役、金沢工業大学虎ノ門大学院准教授 石井大貴)