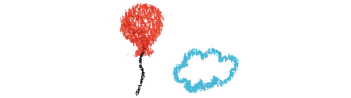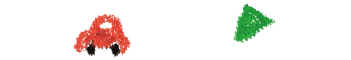政治、経済、文化など多くの分野で日本と深い関わりを持ち、長年にわたり友好的な関係を築いているベトナム。近年では日本に学びに来るベトナム人留学生も多く、中国に次ぐ第二位の人数となるなど人的交流も盛んです。そのベトナムで、約10年にわたり3000人以上の子どもたちに向けたサッカースクールを運営している北口 遥基さん。「サッカーの技術より教育」という理念のもと、日本の幼児教育の良さを取り入れたカリキュラムを実践している北口さんに、日本とベトナムの教育観の違いや幼少期に育みたい「6つの力」などについて伺いました。

Amitie Sports Club Vietnam 代表取締役 北口 遥基氏
1985年、北海道士別市生まれ。高校・大学卒業後、スポーツを通じて子どもの成長を支える教育分野に身を投じる。2014年、ホーチミン市で子ども向けスクールを立ち上げ、事業戦略の構築から現場運営、組織づくり、人材育成まで一貫して牽引。現在はハノイ、ハイフォン、ダナンなどベトナム各地でスクールを展開し、3000名を超える会員が学ぶ場を運営している。これまでに培った教育メソッドと組織運営力を土台に、乳幼児期から一貫して子どもの成長を支える体制づくりを進め、来年初春にはホーチミン市に幼稚園を開園予定。スポーツ教育の枠を超え、未来を生き抜く力を育む場の創造に取り組んでいる。
ベトナムで「6つの力」を育む教育を
石井氏
―まずは、北口さんがベトナムでサッカースクールを運営することになった経緯から教えてください。
北口氏:もともとNPO法人アミティエ・スポーツクラブというところに勤めていて、そこでベトナムに事業展開しようということが決まり、「私が行きます!」と手を挙げてこちらに来ました。とはいえ、私たちはベンチャーの中のベンチャー。ベトナムでどうやって法人を作るのか、それすら分からない状態で飛び込んで、資本金もわずか50万。はじめは「これでどうやって会社をまわしていくの!?」という状態でした(笑)。まずはボロボロの一軒家を借りて、一階をオフィスにして二階に私が住み、三階と四階にベトナム人のスタッフを住ませて、何とかスタートしました。ベトナムに来たのが2013年の6月でしたから、丸12年経って現在13年目を迎えているところです。
石井氏
―まさにゼロからのスタートだったわけですね。今、会員は何人ぐらいいるのですか? また、どうやってスクールを広めていったのですか?
北口氏:今は、3歳から15歳ぐらいまでの子どもたちが約3000人通ってくれています。当初から、私たちのスクールでは「サッカーの技術よりも教育を大事にします」と謳っていたので、そこに魅力を感じた人たちが集まってくれて、その人たちが口コミでどんどん広めていってくれました。あと、普段から私自身もチラシ配りをするのですが、通りがかりの親子にガンガン話し掛けながら、元気いっぱいに配るんです。そういう姿を見て、「何だか分からないけど、この人すごそうだな」と、いわゆる熱みたいなものが伝わった部分もあると思います(笑)。ベトナム人は日本人に一定のリスペクトを持ってくれている方が多いので、「日本人のこの人がこれだけ言うんだから、一度行ってみようかな」と。

笑顔の子どもたちと北口さん(中央)
石井氏
―「サッカーの技術より教育」というと、具体的にはどんなことを教えているのですか?
北口氏:私たちは「6つの力」を上げましょう、と言っています。1つ目は、「他者への想像力」。人の気持ちがきちんと分かるような人間になろうということです。2つ目は、どんなことにもチャレンジできる「高いモチベーション」。3つ目は、何があっても最後まで諦めずに「やり抜く力」。4つ目が、「リーダーシップとフォロワーシップ」。5つ目は、全体を俯瞰して見たり、集団の中で自分が担うべき役割を考えたり内省できる「メタ認知能力」。そして最後は、「ソーシャルマナー」。これは、目上の人に対しての礼節を忘れないとか、物を丁寧に扱うとか、常に感謝の心を持つとかということです。この6つの力を高められるような学びをカリキュラムに組み込んでいるイメージです。
石井氏
―そのカリキュラム自体は、日本のスクールで実施していたのと同じ内容ですか?
北口氏:はい、ほぼ同じです。でも、やはり日本の子どもたちとベトナムの子どもたちは全然違うんですよね。ベトナムの子たちのほうが、集中力を切らさないようにするのが難しい。なので、もともと日本でやっていたことを土台にしつつも、その教育的な部分に、いかに「楽しい」という要素を組み合わせるかを意識しています。いわゆる「エデュテイメント化」ですね。例えば、エデュテイメントレベルが最高で10だとすると、日本では4ぐらいでやっていたところを、ベトナムでは10まで上げるイメージです。いろいろな方法で子どもたちを楽しませながら、みんなの集中力を引き出すように工夫しています。
幼少期こそIQよりEQが大事
石井氏
―私たち日本人からすると、幼少期の教育といえば「礼節を大切にしましょう」とか「靴を揃えましょう」などしつけに近いイメージがあります。ベトナムではどうなのでしょうか?
北口氏:ベトナムで「教育」というと、しつけよりも「勉強」や「スキルの獲得」という意味合いが強いですね。実際にベトナムでは、親御さんの教育投資が盛んで、子どもが小さいうちから様々な習い事をさせるのですが、そのほとんどが英語や数学などのスキルの獲得に偏っています。その現状に対して、私たちは、いわゆる日本的な「当たり前のことを当たり前にやる」とか「常に感謝の気持ちを持つ」とか、そういうことを大切にしましょうと言っています。IQ(知能指数)ではなくEQ(こころの知能指数)を高めることこそ、大事な教育だと考えているのです。

子どもたちと真剣に対話する北口さん
石井氏
―そういう教育観をベトナムの方が聞いたとき、最初はどんな反応をされますか?
北口氏:多くの方は、「まぁ、それも大事だとは思うけれど、それよりも英語ができたほうがいいよね」という感じです。なぜかというと、シンプルに、ベトナムでは英語ができる人は給料が高いのです。あるいは、日本語など他の言語ができる人も給料が高い。日本でも似たような傾向があるかもしれませんが、ベトナムでは日本以上にその幅が大きいんですよね。多分、IQ の高い人材は評価しやすいけれど、 EQ が高い人材の評価は難しいからだと思います。その結果、評価しやすいスキルがある人が優遇されて、給料も上がる。だから親御さんも、英語や他の言語などのスキルを身に付けさせることにより重点を置くのかもしれません。
石井氏
―EQという概念自体が、ベトナムでは理解されにくいということでしょうか?
北口氏:それはあると思います。これは、歴史的な背景も色濃く影響しているのかもしれません。例えば、私たちが考える「EQ が高い人」というのは、自分が何かミスをしたときにきちんと内省して改善していける人。でも、ベトナムの方は一般的に、他責思考で考えることが多いのです。一例として、外で走り回っている子どもがいたとします。親は「そこに石があるから気をつけなさいね」と声を掛けたのに、子どもがその石につまずいて転んでしまった。日本だったら、「ほら、言ったでしょ。次は気をつけなさいよ」と、本人に反省を促すフィードバックをするのが一般的ですよね。でもベトナムでは、親が「石のせいだ!」と石に対して怒るのです。そういう親の姿を見て、子どもたちも「そうか、何か問題が起きたときには、自分以外の人や物のせいにすればいいんだ」と考えるようになるのだと思います。
日本とベトナムの良さを掛け合わせたい
石井氏
―長くベトナムにいる北口さんから見て、日本の教育の良いところや課題というのはどんな風に映っていますか?
北口氏:良いところは、先ほどもお話したような「本人の内省を促す」ということや、「常に他者に配慮する」ということを、家庭や幼稚園・学校などできちんと教えてくれるところだと思います。その結果、自分の感情だけではなく、きちんと周りの人のことも考えながら行動できる子がすごく多いなと。一方で、最近うちにインターンで来てくれている若い子たちなどを見ていると、エネルギーとか欲みたいなものが全くないんですよね。すごくきれいに丸く削られた石のような感じで、自分の殻を打ち破っていこうとする強さがないような気がして。もしかしたら、それが今の日本の教育の課題なのかもしれません。
石井氏
―逆に、ベトナムの子どもたちはどんな感じなのですか?
北口氏:いや、もうすごいですよ。他の子のことは関係なく、「はいはい!僕これやりたい!」と主張して、思い通りにならないと「うわーっ」と暴れちゃう。自己抑制が効いていないと言ってしまえばそうなのですが、自分の欲求を素直にぶつけていくエネルギッシュなところは、すごくいいなと感じる部分でもあります。なので、日本とベトナムのどちらが良いとか悪いではなく、両方の良さをうまく掛け合わせられたらいいなと思うのです。私も、日本的な良さを持ちながら、個人としてしっかり主張するというベトナムの強さ、その両方を兼ね備えた子どもたちを育成できるようなスクールや幼稚園を運営していきたいと考えています。

日本の文化体験イベントでの子どもたちと北口さん(左)
石井氏
―幼少期のお子さんを育てている日本の親御さんたちへ、メッセージをお願いします。
北口氏:日本で生まれ育った私から見ると、ベトナムの人はみんなすごく自然体で生きているなと感じるんです。良くも悪くも、「自分軸」で生きている。たまに自分軸が強すぎて、「もう少し周囲のことも考えようよ」と思うことも多々あるのですが(笑)。一方で日本のお子さんの多くは、周囲への配慮はとてもよくできていると思います。教育のプロである学校の先生や、塾や習い事の先生たちと共に歩んでいけば、子どもたちはそんなに心配しなくても育っていくはず。ですから、そこは必要以上にセンシティブになりすぎずに、もっと自由奔放にやらせる部分もあっていいのかなと。その余白が、子どもたちの「自分の殻を破る力」につながると思うのです。ときには親御さんが余裕を持って見守ることで、将来お子さんが自分でしっかりと羽ばたける力を育んであげられると良いのではないでしょうか。
(聞き手/株式会社LOCOK代表取締役、金沢工業大学虎ノ門大学院准教授 石井大貴)