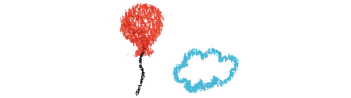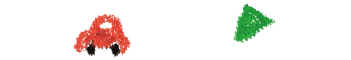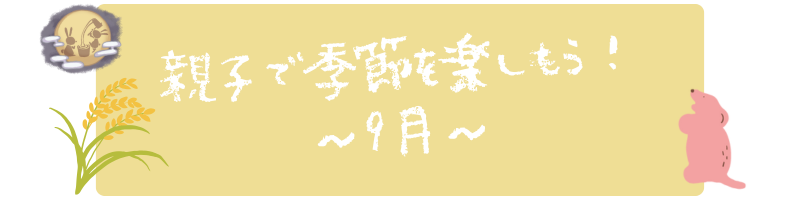
9月は夏の暑さが少しずつやわらぎ、秋の訪れが感じられるようになります。朝晩は涼しくなり、日中との寒暖差が大きくなるため、体調管理には注意が必要です。台風が多く発生する時期ですが、晴れた日には、澄んだ空や心地よい風が感じられます。栗や梨、ぶどうなどの果物をはじめ、サンマやきのこなどのさまざまな食材が旬を迎える季節。敬老の日には、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に、家族で「食欲の秋」を堪能するのも楽しいですね。
9月の自然
長月(ながつき)

9月の和名。「夜長月」が語源とされ、夜が長くなる季節を表しています。古くから和歌や文学にも多く登場し、日照時間が短くなる秋の静けさやもの寂しさを感じさせる表現です。
栗

秋を代表する食材で、9月から10月にかけて旬を迎えます。ほくほくとした食感とやさしい甘みが特徴で、栗ご飯や甘露煮、モンブランなど、多くの料理やお菓子に使われます。
しいたけ

日本の食卓に欠かせない代表的なきのこ。独特の香りと旨味が特徴で、煮物や鍋などさまざまな料理に使われます。食物繊維やビタミンDが豊富な健康食材としても知られています。
露(つゆ)

露とは、夜間や早朝に草木や地面に現れる小さな水滴のこと。空気中の水蒸気が冷えて凝結することで生まれます。特に秋は気温が下がり始め、朝露がよく見られる季節です。
9月の行事
敬老の日

どんな行事なの?
老人を敬い、長寿を祝う日で、毎年9月の第3月曜日とされています。この日は家族で集まり、祖父母や親と一緒に食事をしたり、プレゼントを渡したりすることが多いようです。
どうやって始まったの?
敬老の日の起源は正確にはわかっていませんが、諸説あります。一つは、聖徳太子が「悲田院」という、身よりのない老人や病人のための施設を開いた日が由来だとする説。もう一つは、元正天皇が717年に年号を「養老」とし、養老の滝に御幸した日という説が有名です。
まめ知識
実は、日本の「敬老の日」のように、お年寄りに感謝するための祝日を国全体で設けている国は珍しいとされています。海外では、「母の日」や「父の日」はあっても「祖父母の日」はなかったり、あってもその日が祝日になっていることは少ないのだそうです
9月の記念日
国際識字デー(9月8日)
国際識字デーは、毎年9月8日に制定された国際デーで、識字能力の大切さや、世界における識字率の向上の必要性を広く知らせることを目的としています。1965年にユネスコによって定められ、以来、識字教育の普及と啓発活動が世界各地で行われています。

救急の日(9月9日)
1982年(昭和57年)に、厚生労働省と消防庁によって制定されました。「9(きゅう)9(きゅう)」の語呂合わせが由来です。この日を含む1週間は「救急医療週間」とされ、応急手当の講習や救急功労者への表彰など、全国でさまざまなイベントが行われます。

9月の誕生花
ダリア
メキシコ原産のキク科の球根植物で、鮮やかな花色と、放射状に広がる花びらが特徴的です。花言葉は「華麗」「優雅」。花のサイズが豊富で、大きいサイズは一輪だけでも華やかな存在感があります。優雅なダリアの花束は、さまざまなシーンでギフトとして人気があります。