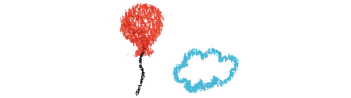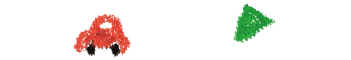今号では、戦国時代の三英傑の一人である豊臣秀吉の幼少期について取り上げます。
秀吉は、1536年に尾張中村(現愛知県名古屋市)の農家に生まれたとされています。低い身分から出世して、「太閤」まで上りつめた話はあまりにも有名です。父は、木下弥右衛門といい、農家でしたが織田信長の父である信秀から出陣の命を受ければ、戦場で戦ったようです。母の大政所(おおまんどころ)は弥右衛門の死後に再婚し、そのタイミングで秀吉は、光明寺という寺に預けられることになりました。しかし、仏像を壊すなど素行が悪く、家に追い返されてしまったそうです。その後も、仕事は長続きしませんでした。このままでは息子がダメになると考えた母は、15歳の秀吉に生活費を渡して家を追い出しました。
秀吉は、木綿針を売り歩きながら清州(現愛知県清須市)から東海道を東に下っていきました。当時、力を持っていた駿府(現静岡県)の今川義元に自分を売り込もうと考えたのです。そして、義元の家臣である松下之綱に草履取りとして仕えたとされています。ところが同僚からの妬みを買い、壮絶ないじめを受け、今川家を出ることになります。
その後、地元に戻った秀吉は、親友の紹介により織田信長の草履取りとして仕えることになりました。信長の草履を懐で温め、その気遣いから一目置かれるようになったことは誰もが知る逸話です。実力次第でのし上がることができる織田家の「風土」は、秀吉にぴったりでした。ようやく自分らしく輝ける場所を見つけ、大出世を果たしていくことになるのです。
秀吉のように、様々な経験から自分を知り、出会いとタイミングを見極めて登り詰める力は、これからの時代を生き抜く子ども達にとっても参考になりそうです。