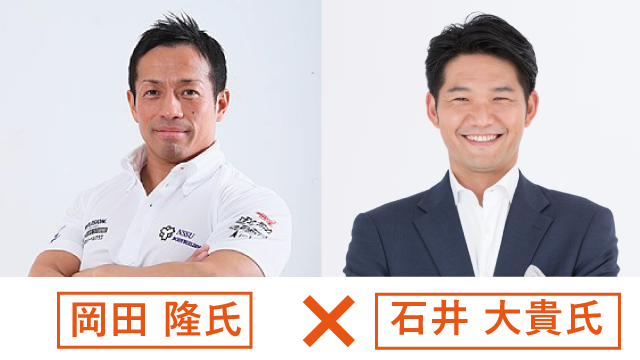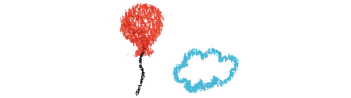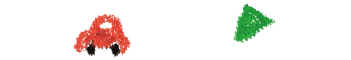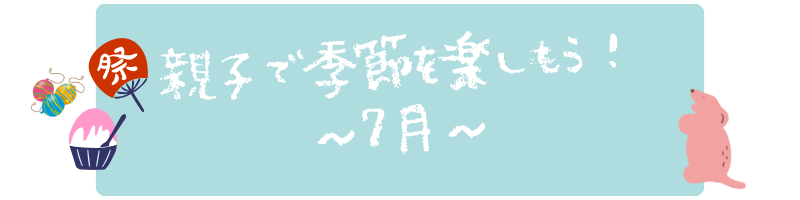
7月に入り梅雨が明けるといよいよ本格的な夏が始まり、全国各地で高温多湿の気候が続きます。また、7月は多くの地域で夏祭りや花火大会が開催され、色とりどりの浴衣を着て参加する人々の姿が見られます。山岳地帯では高山植物が可憐な花を咲かせて見頃を迎え、訪れる登山客の目を楽しませてくれます。熱中症対策に気をつけながら、今年の夏は親子で山登りやハイキングに挑戦してみるのも楽しいですね。
7月の自然
文月(ふみづき)

7月の和名。七夕に書物を夜風にさらす風習があったことから「文披月(ふみひろげづき)」、「稲穂が膨らむ月」の意味から「穂含月(ほふみづき)」が由来だとする説などがあります。
トウモロコシ

7~8月に旬を迎える野菜。もともとメキシコやアメリカを中心に栽培されていて、日本には16世紀ごろ伝わったとか。食物繊維やミネラル、ビタミンなどの栄養価が高い野菜です。
スイカ
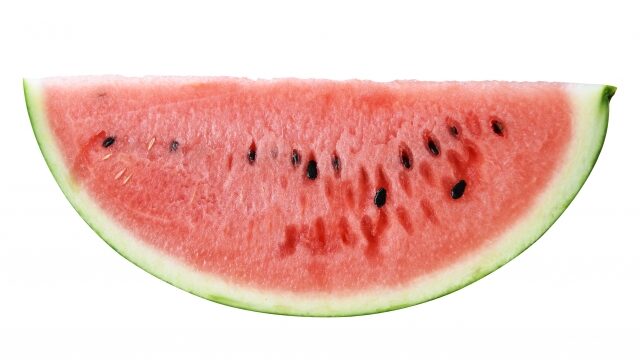
夏の果実の王様として親しまれているスイカ。果肉の成分のうち90%が水分で、約9.5%が糖分だそう。果糖は冷やすと甘みが強くなるので、よく冷やして食べるのがおすすめです。
山開き

毎年一般の方の登山が許可される日。かつて山は信仰の対象で、庶民の登山は禁じられていました。しかし、江戸時代半ばには一定期間だけ解禁され、それを「山開き」と称しました。
7月の行事
土用の丑の日

どんな行事なの?
土用とは、暦の上で季節が変わる時期のことで年4回あります。この内、夏の土用の期間の丑の日を「夏の土用の丑の日」といい、この日にうなぎを食べると体に良いとされています。
どうやって始まったの?
日本には古来より、丑の日にうの付く食べ物(梅干し、瓜など)を食べて無病息災を願う習慣が。そこにうなぎが加わったのは、「夏はうなぎが売れない」と悩むうなぎ屋に、蘭学者の平賀源内が「土用丑の日」の看板を出すよう提案したのがきっかけとする説が有力です。
まめ知識
2025年は、夏の土用の丑の日が2回あります(7月19日と7月31日)。これは、18日間ある土用の期間のうちに、12日周期の「丑の日」が2回巡ってくるためです。この場合、1回目の丑の日を「一の丑」、2回目の丑の日を「二の丑」と呼びます。
7月の記念日
世界人口デー(7月11日)
1987年7月11日に世界の人口が50億人に達したことを記念して、1989年、国連開発計画の運営評議会が人口問題の緊急性と重要性への関心を高めるために制定した記念日。翌年12月の国連総会において、正式に国際記念日(国際デー)として制定されました。
自然公園の日(7月21日)
1957年のこの日に、自然公園法が施行されたことから制定されました。自然公園法は、自然公園を守り、親しんでもらうことを目的としており、環境省は毎年記念日である7月21日から8月20日までの1カ月を「自然に親しむ運動」期間と定めています。
7月の誕生花
ユリ
 ユリ科の球根植物。白やピンクなど、大ぶりで香りの良い花を咲かせます。花言葉は、「純粋」「華麗」「陽気」。ユリは切り花になってもつぼみが次々と開くので、花を長く楽しめるのも魅力。ユリという名の由来は、茎が高く風に揺れる様子から「揺り」だとされています。
ユリ科の球根植物。白やピンクなど、大ぶりで香りの良い花を咲かせます。花言葉は、「純粋」「華麗」「陽気」。ユリは切り花になってもつぼみが次々と開くので、花を長く楽しめるのも魅力。ユリという名の由来は、茎が高く風に揺れる様子から「揺り」だとされています。