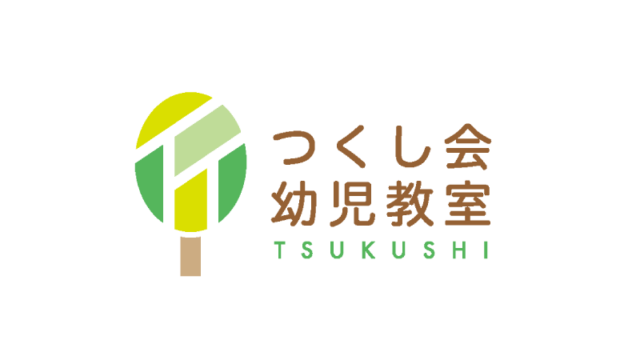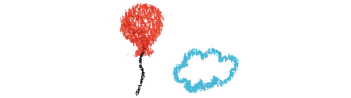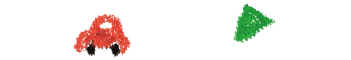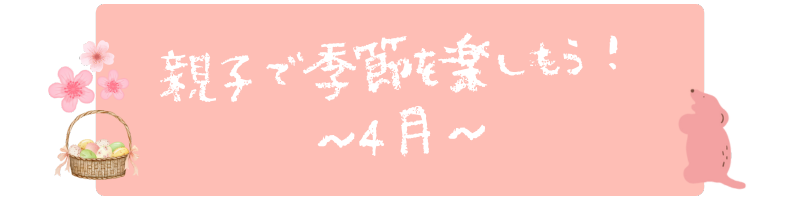
4 月といえば、入園式・入学式や進級など、新生活がスタートする節目の季節。期待と不安の両方を感じているお子さんも多いかもしれません。春は1 年のうちで寒暖差が一番大きく、体は交感神経の働きが優位になるため緊張状態が続きやすくなります。さらに、生活の変化により、普段よりストレスを感じることが増える場合も。規則正しい生活や良質な睡眠を心掛け、散歩や適度な運動をするなど、親子で気分転換をしてみるのもおすすめです。
3月の自然
卯月
 4月の和名。由来は、卯の花の咲く月、田植えの月 (植月)など、いくつかの説があります。4月は他に、木葉採月(このはとりつき)、花残月(はなのこりづき)などの雅な呼び名も。
4月の和名。由来は、卯の花の咲く月、田植えの月 (植月)など、いくつかの説があります。4月は他に、木葉採月(このはとりつき)、花残月(はなのこりづき)などの雅な呼び名も。
うど
 ウコギ科タラノキ属の多年草。数少ない日本原産の野菜のひとつで、香りが強いのが特徴。旬の時期は3月~5月で、古くから春を感じさせる山菜として親しまれてきました。
ウコギ科タラノキ属の多年草。数少ない日本原産の野菜のひとつで、香りが強いのが特徴。旬の時期は3月~5月で、古くから春を感じさせる山菜として親しまれてきました。
びわ
 ふっくらしたオレンジ色の果実で、さっぱりとした味わいが人気。旬は3月~6月頃。果実にはビタミンやミネラルが含まれ、葉に含まれる成分は古くから薬用とされていました。
ふっくらしたオレンジ色の果実で、さっぱりとした味わいが人気。旬は3月~6月頃。果実にはビタミンやミネラルが含まれ、葉に含まれる成分は古くから薬用とされていました。
寒の戻り
 寒の戻りとは、暖かくなってきた3月~4月に、一時的に寒さがぶり返す現象のこと。似た言葉に「花冷え」がありますが、「花冷え」は桜の時期の短い間にだけ使われる表現です。
寒の戻りとは、暖かくなってきた3月~4月に、一時的に寒さがぶり返す現象のこと。似た言葉に「花冷え」がありますが、「花冷え」は桜の時期の短い間にだけ使われる表現です。
4月の行事
花まつり
 どんな行事なの?
どんな行事なの?
仏教の祖である釈迦の誕生日を祝う行事です。寺院などでは、花で飾った花御堂(はなみどう)の中に釈迦の像を安置し、この像にひしゃくで甘茶をかけて無病息災などを祈ります。
どうやって始まったの?
花まつりは、中国から伝わった行事です。釈迦が生まれたとき、天から降りてきた龍王が、清い水を釈迦に注ぎかけて産湯を使わせたという伝説が由来となっています。花御堂は、釈迦が生まれた花園をかたどったもの、甘茶は龍王が注いだ水の代わりとされています。
まめ知識
「灌仏会(かんぶつえ)」「仏生会(ぶっしょうえ)」などとも呼ばれています。釈迦の生誕が4月8日とされているため、花まつりはこの日に開催されるのが一般的です。ただし、旧暦の4月8日や月遅れの5月8日に開催するお寺もあり、地域によって異なることも。
4月の記念日
ヘリコプターの日(4月15日)
 1986年、全日本航空事業連合会が、「モナ・リザ」で有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日である4月15日を「ヘリコプターの日」に制定。彼は画家のみならず発明家としても知られ、ヘリコプターの原理を考案したことから、この日が記念日として定められました。
1986年、全日本航空事業連合会が、「モナ・リザ」で有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日である4月15日を「ヘリコプターの日」に制定。彼は画家のみならず発明家としても知られ、ヘリコプターの原理を考案したことから、この日が記念日として定められました。
図書館記念日(4月30日)
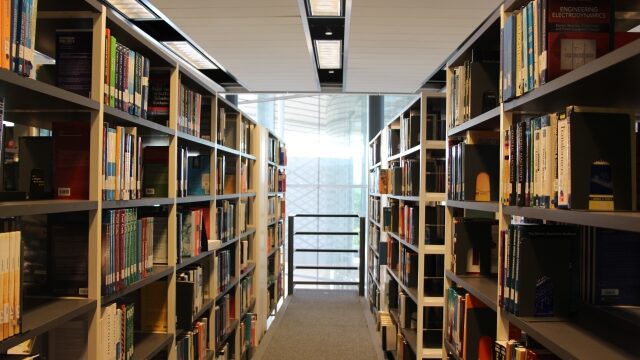 1950年のこの日に「図書館法」が公布されたことから、日本図書館協会が記念日として制定。同協会は毎年ポスターを作製し、各地の図書館などに掲示しています。また、この日に続く5月1日~31日を「図書館振興の月」とし、様々なプログラムを実施しています。
1950年のこの日に「図書館法」が公布されたことから、日本図書館協会が記念日として制定。同協会は毎年ポスターを作製し、各地の図書館などに掲示しています。また、この日に続く5月1日~31日を「図書館振興の月」とし、様々なプログラムを実施しています。
4月の誕生石
カスミソウ
 ナデシコ科カスミソウ属の花。漢字で書くと「霞草」、英名では「Baby’s breath(赤ちゃんの吐息)」という名のとおり、小さな花を無数に咲かせ、満開を迎えたときには霞がたなびいているように見えます。花言葉は、「幸福」「感謝」「親切」「清らかな心」「無邪気」。
ナデシコ科カスミソウ属の花。漢字で書くと「霞草」、英名では「Baby’s breath(赤ちゃんの吐息)」という名のとおり、小さな花を無数に咲かせ、満開を迎えたときには霞がたなびいているように見えます。花言葉は、「幸福」「感謝」「親切」「清らかな心」「無邪気」。